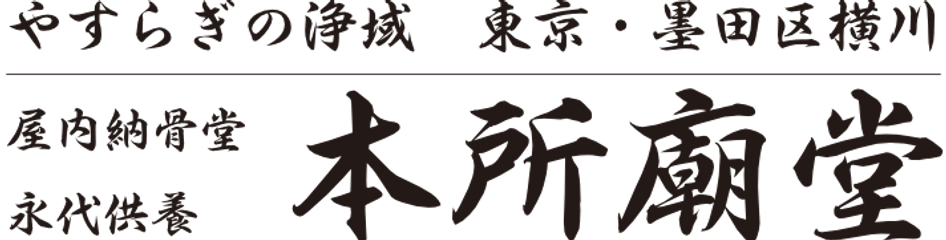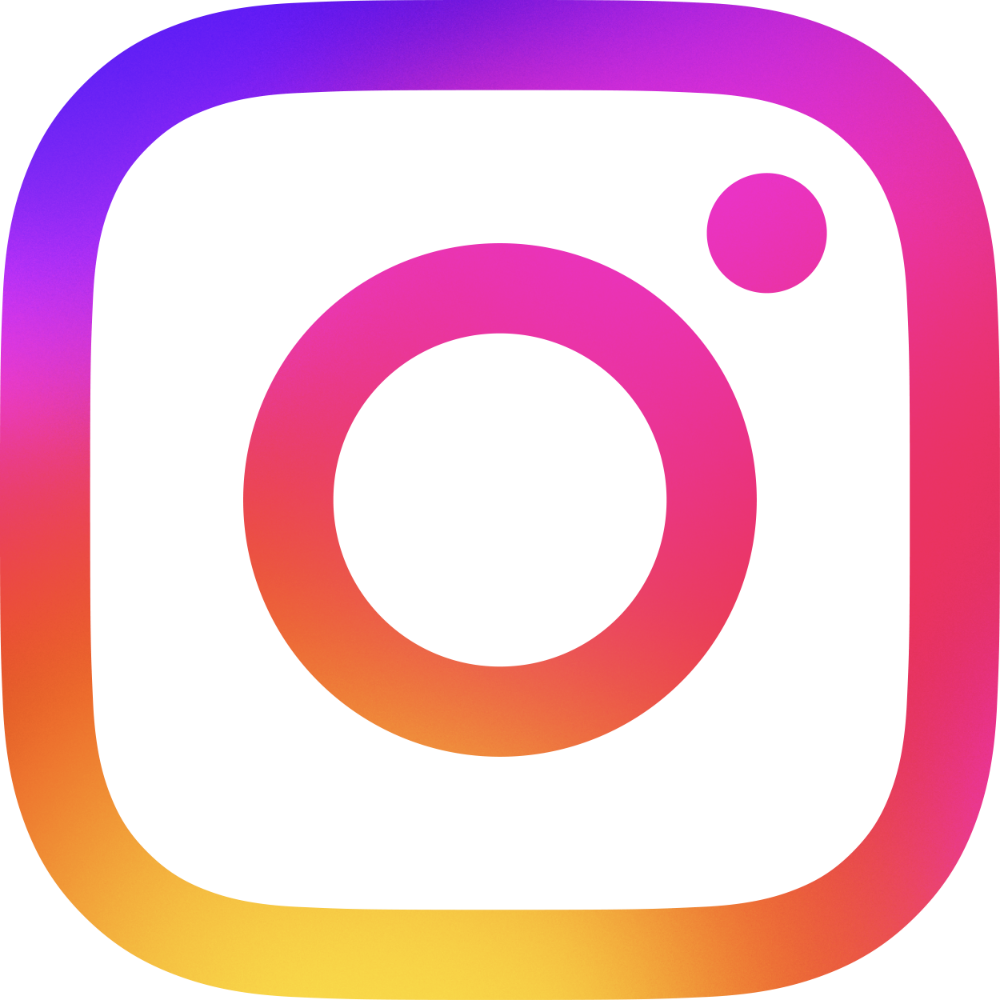供養
本所廟堂納骨供養
故人様の生きた証であるご遺骨を骨壺骨袋の状態で特別厨子に納め、納骨堂の供養棚に安置し、お題目法華経を毎朝毎夕聴いていただき故人の霊魂が安らかであることを祈ります。
単に納骨するだけでなく、お題目法華経をお聴かせすることは、故人にとって最大限に丁寧なご供養になります。
納骨の時期は四十九日忌や百カ日忌、一周忌や年回忌など、節目の法要に合わせて行われることが多いです。
葬儀供養
故人の霊魂を弔い、冥福を祈るために行われる一連の儀式や行為を指します。
葬儀式自体が最も重要な供養の場であり、僧侶による読経、参列者の焼香、供物や供花の奉納などが行われます。
その目的は、故人の魂があの世で安らかに過ごせるように祈ること、そして残された遺族が故人の死を受け止め、悲しみを乗り越えるための心の整理の場とすることにあります。
お釈迦様の最大の教えであるお題目法華経を皆で読み、故人に聴いていただくことが、葬儀供養の本質と言えるでしょう。
永代供養
先祖父母家族のお墓をできることなら永く守って承継していきたいという気持ちは誰にでもあると思います。
しかし、昨今における核家族化や代々の土地から離れ、維持や管理が難しい遺族に代わり、お寺が故人を永代に供養します。
承継者がいない方や、お墓の管理に不安がある方にとって、経済的・精神的な負担を軽減できる選択肢として近年注目されています。
先祖供養
私たちが生きているのは両親とご先祖様がいるからです。
その繋がりを毎日24時間365日忘れずに生きることは難しいでしょう。
もしかしたら長い間忘れてしまっている人もいるかもしれません。
悲しいですが、ご先祖様を近くに感じる機会がなく、核家族化が進んだ昨今では仕方のないこととも思います。
ご先祖様を供養することによって、供養を施す私たちも、供養を受け取るご先祖様も共に幸せになることができます。
法事(年回忌)
故人の冥福を祈り、追善供養のために行われる法要です。
一般的には、故人の命日や定められた年忌(初七日、四十九日、一周忌、三回忌など)に合わせて行われます。
僧侶による読経や法話、参列者による焼香などが主な内容です。
故人を偲び、遺族や親族が集まることで、故人の供養とともに、故人との繋がりや思い出を共有し絆を深める機会になります。
水子供養
この世に生を受けることができなかった赤ちゃんの冥福を祈る供養のことです。
生まれる前に亡くなった命は「水子」と呼ばれます。水子のためにお題目法華経を供養することで水子は安心をして、つぎの世で安らかに過ごせることができます。
水子供養は、亡くなった赤ちゃんのためだけでなく、悲しみを抱えるママとパパ、家族のケアとしても重要な意味を持ちます。供養を通して、失われた命と向き合い、悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための心の区切りとするのです。
ペット供養
家族の一員として共に過ごしたペットへの感謝の気持ちと安らかであることを願って人間と同様に弔い冥福を祈ります。
法華経には人間以外の動物も成仏できると説かれています。
人形供養
人形は長年大切にしてきた人形やぬいぐるみを対し単にゴミとして処分するのではなく、魂が宿ると考えられてきた人形たちに、感謝と別れを告げ、安らかに眠ってもらうことを願って行われます。
お経を読み、お焚き上げをしたりする形式が一般的です。
持ち主の思い出や愛着が詰まった人形たちを丁寧に扱い、感謝の気持ちと共に手放すことで、持ち主自身の心の整理にも繋がります。
施餓鬼供養
仏教における供養の一つで、飢えや渇きに苦しむ餓鬼道に堕ちた霊や、供養を受けられない無縁仏などに対し、食べ物や飲み物を施し、その苦しみから救い出すことを目的とした法会です。
その由来は、お釈迦様の弟子である阿難が餓鬼に寿命を予告された際、お釈迦様の教えに従い、陀羅尼を唱えながら施しを行ったところ、餓鬼が救われたという説話に基づくとされています。
日本では、お盆の時期に先祖供養と合わせて行われることが多く、精霊棚に食べ物を供えたり、お寺で法要が営まれたりします。施餓鬼供養は、亡くなった方々への慈悲の心を表すとともに、自身の徳を積む行いとしても大切にされています。
土地清め供養
土地に対して行われる供養や儀式です。 その目的は、土地に溜まったとされる負のエネルギーや過去の出来事による影響を浄化し、清らかな状態に戻すこと、土地の神様や自然への感謝を捧げること、そして今後の安寧や繁栄を祈願することなどが挙げられます。
お経を読み、お供え物をし、塩や酒を撒くなどの儀式が行われます。建物を建てる前に行われる地鎮祭も、広義には土地清め供養の一種と言えるでしょう。
家屋清め供養
住居や建物に対して行われる供養や儀式です。 その主な目的は、家の中に溜まったとされる良くない気や過去の住人の影響などを浄化し、住む人が安心して快適に暮らせるようにすること、そして家を守る神様やご先祖様への感謝を捧げることです。
お経をあげ、塩や酒、米などを家の四隅や中心に撒き、お供え物をするなどの儀式が行われます。新築時や中古物件への入居前、あるいは事故や不幸があった後などに行われることがあります。
家屋清め供養は、物理的な清掃だけでなく、精神的な安心感を得て、新たな生活を気持ちよく始めるための大切な儀式と言えるでしょう。
年回忌法要
故人の冥福を祈り、定められた年に行われる仏教の追善供養の儀式です。 亡くなった翌年の一周忌を最初とし、その後、**三回忌、七回忌、十三回忌…**と、年数を重ねて行われます。
主な目的は、故人を偲び、その霊を慰めるとともに、遺族や親族が集まり、故人との思い出を語り合い、絆を深めることです。また、仏教の教えに触れ、自身の生き方を見つめ直す機会ともされます。
僧侶による読経や参列者の焼香などが行われます。三十三回忌や五十回忌をもって「弔い上げ」とし、年忌法要を終えることが多いですが、地域や宗派、家の考え方によって異なります。
改葬供養
現在埋葬されているご遺骨を別の納骨施設に移す際に行われる供養のことです。 お墓の引越しとも言えます。
改葬には、墓じまい(現在のお墓の撤去・整理)と、新しい納骨先への納骨という二つの側面があり、それぞれの段階で供養が行われることがあります。具体的には、**閉眼供養(魂抜き)**として、現在のお墓に宿る故人の魂を抜き取る儀式や読経が行われ、遺骨を取り出した後に行われることが多いです。
そして、新しい納骨先へご遺骨を納める際には、**開眼供養(魂入れ)**として、新たな納骨施設に故人の魂を迎え入れる儀式や法要が営まれます。これらの供養は、故人の冥福を祈り、遺族の心の区切りをつける大切な意味を持ちます。